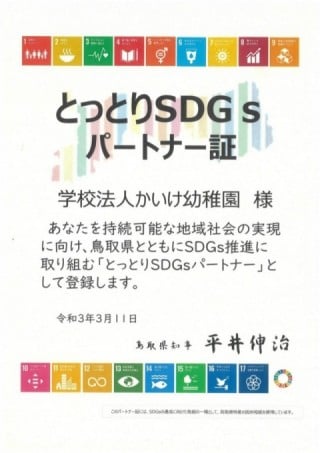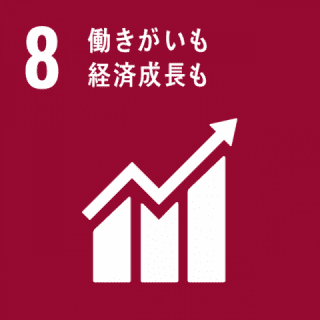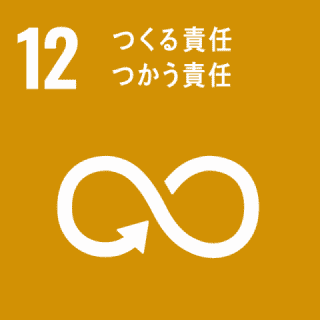SDGsの取り組み
学校法人かいけ幼稚園SDGs推進活動 「じぶんごとぷろじぇくと」
SDGs(Sustainable Development Goals)とは

SDGsとは「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」のことで、2015年9月の国連サミットで採択された2030年までの国際目標です。
「地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)」という誓いのもと、人間、地球及び繁栄のための行動計画として、「貧困」「健康と福祉」「教育」「働きがい」「気候変動」など17の目標と169のターゲットで構成されています。
SDGsは発展途上国のみならず先進国自身が取り組むユニバーサルなものであり、日本でも積極的に取り組まれています。
とっとりSDGsパートナー制度に登録しています!
★とっとりSDGsパートナーになりました!!(R3.3~)★
学校法人かいけ幼稚園は、鳥取県の「とっとりSDGsパートナー」制度に賛同し、パートナーになりました!
SDGsを鳥取県と共に推進し、SDGsのゴール達成を目指します。
かいけ心正こども園での取り組み
当園は地域社会の一員として、積極的な社会貢献活動に取り組み、次世代へ繋がる豊かで暮らしやすい街づくりと地域の発展を目指します。
2.飢餓をゼロに
本園の特色にもある「食育」の活動の中では、子どもたちが実際に野菜を育て、それを自園給食で食べるという”食のサイクル”を体感出来る取り組みをしています。自分たちが育てたものを食べることで、苦手な野菜も食べられたり、「もったいない」の気持ちが養われたりします。
さらに、給食の残飯の量を見える化する仕組みを始めました。日々の残飯量をイラストで示すことで、子どもたちが残飯量に興味を持ち、昨日よりも今日、今日よりも明日の残飯を減らせるよう、自分に出来ることを考えるきっかけになります。
3.すべての人に健康と福祉を
各ご家庭から古着を回収し、発展途上国に送ることで、現地の子どものポリオワクチン接種に繋がる『古着deワクチン』の活動に取り組んでいます。第一回目の活動(令和3年度 春)では沢山のご寄付を頂きました。子どもたちと一緒に梱包をしたり、袋のデコレーションをしたりすることで、子どもたち自身も「わたしにも出来ることがある」ということに気付くことが出来ました。
4.質の高い教育をみんなに
本園の5つの特色(造形教育・英語教育・モンテッソーリ教育・食育・良い生活習慣)を中心とした様々な活動や経験を通して、人生の基礎となる心のねっこを育てます。子どもたちは活動の中で、面白さを感じたり、疑問をもったり、葛藤したり、満足したりと、様々な感情や知識を獲得します。興味のあること・楽しいと思うことに没頭できる環境の中で、遊びを通して豊かな感性や創造性を養います。
8.働きがいも経済成長も
本園は、職員みんなで声を掛け合い、一人ひとりのワークライフバランスにすることで、働きやすい職場環境を作っています。さらに、積極的に研修会等に参加することで、職員のスキルアップや自信に繋げます。
また、地域企業との連携したイベントを開催したり、障害福祉サービス事業所等の商品等の積極的な購入を行っています。すべての人が、働きがいを感じながら地域に貢献できる未来を目指します。
10.人や国の不平等をなくそう
園生活の中で、性別や年齢、国籍や宗教の違いは関係ありません(プライバシーを考慮しないければならないことを除く)。大人も、子どもも、あの子もこの子も、みんな同じ活動に取り組み、一緒に喜んで、一緒に泣いて、一緒に成長していきます。
また、職員も男女・国籍問わず採用しています。すべての人が「毎日行きたい」と思える園・職場を目指しています。
12.つくる責任 つかう責任
本園では食育の一環として、園の畑を所有しています。そこで育てた野菜を給食で頂くことで、食べ物の大切や作ってくれた人への感謝の気持ちを感じることが出来ます。給食の際は、沢山食べる事よりも、食べられる量をしっかり噛んで味わいながら頂くことを大切にしています。
また、古着を回収して発展途上国へ送ることで現地の方の雇用やポリオワクチンの接種につながる「古着deワクチン」の活動も実施しています。子どもたちも梱包作業や配送作業に携わることで、世界には様々な面で困っている人がいることに気付き、ものを大切にする気持ちを養います。
さらに、古くなった園バスをリサイクルステーションに改装し、資源ごみ回収も行っています!(※利用は園の関係者に限ります) かわいいライオンバスに乗れるワクワク感と、リサイクルの大切さを感じる事の出来る一石二鳥の活動です♪①古紙 ②ペットボトル(キャップ含む) ③缶(スチール・アルミ) ④古紙 ⑤食品トレー を回収しています。時間や曜日にとらわれず、親子で楽しく分別をしながらリサイクル活動を行うことが出来ます! リサイクルの過程で得た収益は、開発途上国へ寄付しています。令和4年度は15000円分の寄付を行いました。
14.海の豊かさを守ろう
毎日、どこまでも広がる日本海を眺められることは本園の魅力の一つです。子どもたちにとって「綺麗な海」が身近にあることが当たり前になるように、海に親しみを持てるような活動を取り入れています。
また、海岸遊びを兼ねて海岸の清掃活動も行います。地域の美しい環境を自分たちの手で守っていくという意識を育てます。
15.陸の豊かさも守ろう
日南町の山で里山再生活動を行っています。題して「心正の森大作戦」!荒れた森を開拓したり、苗木を採取して育てたり、落ち葉プールを作ったり…。不必要な木を伐採することで他の植物の生長を促したり、店で買った苗でなく、山から直接とれた苗を育てるなど、自分の住んでいる土地の緑を大切にする心を育てています。将来的には、みんなで遊んで学べる森になるよう、在園生・卒園生が力を合わせて取り組んでいますよ♪
16.平和と公平をすべての人に
保育のプロとして、様々な視点から子育てをサポートしています。職員は分野を問わず、様々な研修に積極的に参加しています。子育ての不安や困り事は何でも相談してください。
また、子どもに対してあらゆる虐待を発見した場合、こども園の責務として、必要機関と連携を取り、子どもたちの安全と人権を守るために善処します。